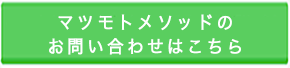今回は、聞き手との「漫才のしかた」がテーマです。安心してください。本当に漫才をするわけではありません。
プレゼンテーションやスピーチなど、聞き手を魅了するのに漫才の方法を利用するというお話です。
説明がスムーズ過ぎると、聞き手を引きつけられない
漫才と言えばボケとツッコミ。あなたにはボケ役、聞き手はツッコミに回ってもらうように話の構成をするのです。前置きはこの辺で、まずはやってみましょうか。
最初はボケ・ツッコミのない、普通の説明の仕方の例を挙げてみましょう。
「話し方を伝わるものにしようと思ったら、たくさんの言葉を尽くしてずーっと相手に話し続けるのは逆効果になります。なぜなら聞いている人は、はじめて聞くあなたの話を理解するのに時間もかかりますし、なにより休みなく多くの言葉を聞かされるのは聞いているほうとしては疲れてしまうものです。相手にしっかり伝えようと思ったら、色々な内容を一気に話すのではなく、一つの内容をしゃべったら、聞き手がその内容を理解するための間を作るようにするのです。つまり内容と内容の間に黙る時間をつくることが大切なのです。」
字で読むとなんの問題もない説明に見えると思います。しかし、これを耳で聞いていると、気づきにくいかもしれませんが、説明がスムーズに続きすぎて、聞いていて驚きや引きつける力が足りないのです。
そこで、漫才風にボケとツッコミの形で構成してみます。
ボケ(以下ボ)「伝わる話し方のコツは色々あるけど、一番大事なことって知ってる?」
ツッコミ(以下ツ)「え、なに?」
ボ「黙ること!」
ツ「そんなアホな!しゃべらなあかんのに黙る?」
ボ「そらビックリするわね。でもだまらんとずーっと説明を続けられたら、どう思う?」
ツ「ちょっとしんどいかなぁ」
ボ「そう、ちょっとは休ましてくれんと、聞いてるほうは疲れるでしょ」
ツ「確かに」
ボ「だから伝えたいことがあったら、ずっとしゃべったらあかんねん」
ツ「どないすんのん?」
ボ「まとまった内容を一つしゃべったら黙る。しゃべったら黙る。ちゃんと黙る時間を作るようにするんや。」
いかがでしょうか?
次に、このやりとりからツッコミのコメントを抜いてボケだけにしてみてください。ボケの台詞を言ってひと呼吸待てば、聞き手は間違いなくツッコミの台詞を言いたくなるはずです。これこそ、引きつけるコツ!聞いている方が話し手の言葉に反応せざるを得ない作りにして、話に引き込むのです。
説明なしに結論を言い切る
コツは、ロジックを背景や具体例から結論まで順に積み上げていかないこと。一番最後の結論を、なんの前提も説明もなしに言い切るのです。そうすると聞き手は、「え?どういうこと?」と聞きたくなります。あとは「根拠は?」「具体例は?」など聞き手はこう聞いてくるだろうなと言うことを想像しながら、付け加えていくようにします。
口頭による説明は、とにかくその瞬間瞬間で聞き手を引きつけ続けられなければ、聞き手はあなたのストーリーからどんどん脱落していきます。それでは伝わる話し方にはなりません。(隙のなさが求められる、論文やコンサルティングのレポートなら、積み上げ式の方が好まれますので、ご注意ください。)
オーディエンスと漫才ができるよう、ぜひ話を組み立ててみてください。効果は面白いほど出てきますよ。
この記事は、2019年1月から12月まで週刊東洋経済に連載したコラム「必ず伝わる最強の話術」に 加筆修正を加えたものです。
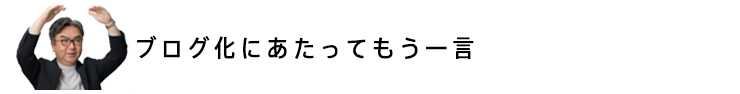
 松本和也(まつもと・かずや) / 音声表現コンサルタント・ナレーター・司会・ファシリテーター。1967年兵庫県神戸市生まれ。私立灘高校、京都大学経済学部を卒業後、1991年NHKにアナウンサーとして入局。奈良・福井の各放送局を経て、1999年から2012年まで東京アナウンス室勤務。2016年6月退職。7月から「株式会社マツモトメソッド」代表取締役。アナウンサー時代の主な担当番組は、「英語でしゃべらナイト」司会(2001~2007)、「NHK紅白歌合戦」総合司会(2007、2008)、「NHKのど自慢」司会(2010~2011)、「ダーウィンが来た!生きもの新伝説」「NHKスペシャル(多数)」「大河ドラマ『北条時宗』・木曜時代劇『陽炎の辻1/2/3』」等のナレーター、「シドニーパラリンピック開閉会式」実況に加え、報道番組のキャスターなどアナウンサーとしてあらゆるジャンルの仕事を経験した。株式会社 青二プロダクション所属
松本和也(まつもと・かずや) / 音声表現コンサルタント・ナレーター・司会・ファシリテーター。1967年兵庫県神戸市生まれ。私立灘高校、京都大学経済学部を卒業後、1991年NHKにアナウンサーとして入局。奈良・福井の各放送局を経て、1999年から2012年まで東京アナウンス室勤務。2016年6月退職。7月から「株式会社マツモトメソッド」代表取締役。アナウンサー時代の主な担当番組は、「英語でしゃべらナイト」司会(2001~2007)、「NHK紅白歌合戦」総合司会(2007、2008)、「NHKのど自慢」司会(2010~2011)、「ダーウィンが来た!生きもの新伝説」「NHKスペシャル(多数)」「大河ドラマ『北条時宗』・木曜時代劇『陽炎の辻1/2/3』」等のナレーター、「シドニーパラリンピック開閉会式」実況に加え、報道番組のキャスターなどアナウンサーとしてあらゆるジャンルの仕事を経験した。株式会社 青二プロダクション所属