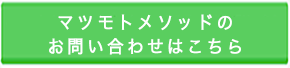披露宴や送別会などでのスピーチのしかたは第10回でお伝えしました。
今回は、披露宴に限らず様々なパーティーなどで、司会をつとめなくてはならなくなったときのコツをご紹介します。
目的以外は考える必要ない
まず、司会の最も大切な役割から。当たり前ですが、司会は全く目立つ必要はありません。何よりも大切なのは、参加した人に心地よい時間を過ごしてもらうこと。そのためにまず行ってほしいのは、パーティーの目的と参加者の確認です。
目的は、参加者に楽しんでもらうことに加え、披露宴でしたら新郎新婦をお祝いすること、一般的なパーティーでしたら登壇者に気持ちよく話してもらうことなどがあると思います。まずは、こうした目的以外のことは、それほど考える必要はないんだと思って頂きたいのです。
「言い間違えないように」「スマートに見えるように」など自分をよく見せようとしなくていいと思えれば、無用な緊張は感じずに済みます。
私もアナウンサー時代、間違わないように、失敗しないようにと思っていた時は、司会の仕方がギクシャクすることが多かったのですが、「下手に思われてもいい。視聴者の方に、中身をちゃんとわかりやすく伝えることに全力を注ごう」と思えるようになってからは、変に緊張することがずいぶん減りました。
参加者と会の流れを把握する
次に、参加者の確認です。確認する内容は、参加者の名前や所属する会社の読み方はもちろん、披露宴でしたら新郎新婦との、一般的なパーティーでは挨拶が予定されている来賓の方との関係性などです。ここを怠っていると、予定にない方が挨拶に立ったりした場合に対応できず、あたふたしてしまいます。ここまでが最低限の準備です。
式次第は、披露宴でしたらしっかりと書き込まれたもの、一般的なパーティーでも挨拶する方の順番など、おおよその流れは準備されていると思います。
大切なのは、この式次第があることで安心しないことです。というのも、パーティーの挨拶は、想定以上に長く話す方が出てくることが、頻繁にあります。何もしないでいると、予定している時間を超過してしまい、参加者の中にはそのことを不快に思う方もいるかもしれません。なんとか時間内に終えるためにはあらかじめ、「3人目の挨拶まで○分、残り2人で○分」など、式次第の項目ごとに終了時間をおおよそでもいいので、決めておきましょう。
次に、スピーチをする方のところに事前にご挨拶に行き、スピーチする順番と出番の予定時間を伝えます。そのときに「大変恐縮ですが、できれば○分を超えないように話していただけると。。。」とスピーチの長さについても、丁重にお願いするようにします。特に後半にスピーチする方には「進行の具合によっては、短く話して頂かなくてはいけないかもしれません。その時はどうか助けてください」と伝えておくようにします。あらかじめ心づもりをして頂くわけです。
本番中は、あとで話す方のところに随時足を運んで、進行の具合を報告に行っておくと、ほぼ100%手短に話して頂けます。
話し方で気をつけるのは、ちゃんと全員の方に聞き取ってもらえるよう、ゆっくりはっきり話すこと。たったこれだけで十分です。
この記事は、2019年1月から12月まで週刊東洋経済に連載したコラム「必ず伝わる最強の話術」に 加筆修正を加えたものです。
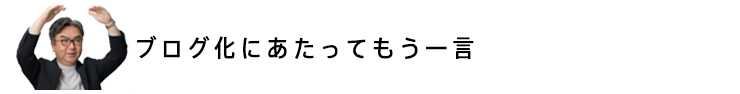
 松本和也(まつもと・かずや) / 音声表現コンサルタント・ナレーター・司会・ファシリテーター。1967年兵庫県神戸市生まれ。私立灘高校、京都大学経済学部を卒業後、1991年NHKにアナウンサーとして入局。奈良・福井の各放送局を経て、1999年から2012年まで東京アナウンス室勤務。2016年6月退職。7月から「株式会社マツモトメソッド」代表取締役。アナウンサー時代の主な担当番組は、「英語でしゃべらナイト」司会(2001~2007)、「NHK紅白歌合戦」総合司会(2007、2008)、「NHKのど自慢」司会(2010~2011)、「ダーウィンが来た!生きもの新伝説」「NHKスペシャル(多数)」「大河ドラマ『北条時宗』・木曜時代劇『陽炎の辻1/2/3』」等のナレーター、「シドニーパラリンピック開閉会式」実況に加え、報道番組のキャスターなどアナウンサーとしてあらゆるジャンルの仕事を経験した。株式会社 青二プロダクション所属
松本和也(まつもと・かずや) / 音声表現コンサルタント・ナレーター・司会・ファシリテーター。1967年兵庫県神戸市生まれ。私立灘高校、京都大学経済学部を卒業後、1991年NHKにアナウンサーとして入局。奈良・福井の各放送局を経て、1999年から2012年まで東京アナウンス室勤務。2016年6月退職。7月から「株式会社マツモトメソッド」代表取締役。アナウンサー時代の主な担当番組は、「英語でしゃべらナイト」司会(2001~2007)、「NHK紅白歌合戦」総合司会(2007、2008)、「NHKのど自慢」司会(2010~2011)、「ダーウィンが来た!生きもの新伝説」「NHKスペシャル(多数)」「大河ドラマ『北条時宗』・木曜時代劇『陽炎の辻1/2/3』」等のナレーター、「シドニーパラリンピック開閉会式」実況に加え、報道番組のキャスターなどアナウンサーとしてあらゆるジャンルの仕事を経験した。株式会社 青二プロダクション所属