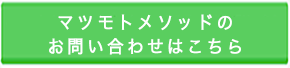必ずしなければいけないのに意外と苦手な人が多い自己紹介。今回は私なりのコツをお伝えします。
自己紹介はいつもだいたい同じという方もいると思います。名前と所属部署や役職、担当している仕事くらい。最後は「よろしくお願いします」でしめる。
こんな感じではないでしょうか?最低限の情報で十分という考えもわかりますが、せっかく話すのですからもう少し工夫してみませんか?
相手によって、自己紹介の中身を変えよう
いちばん大切なポイントは、自己紹介は聞き手によって中身を変える習慣をつけることです。
配属された新人に向けてでしたら、名前以外に自分がどんな仕事を担当しているのかわかりやすく伝えてあげなくてはいけませんよね。
転勤先の新しい職場の人に向けてなら、自分のこれまでの職歴はもちろん、旅行で一度来たことがあるなど、新しい任地との関わりがあれば、そのことを話した方が、受け入れる側も嬉しくなるかもしれません。
職場ではなく、例えばPTA役員に選ばれたときの自己紹介でしたら、自分の職業よりも休みの過ごし方や子どもの教育にかける思いなどのほうが大切な情報になるでしょう。
いずれにせよ、目の前で自己紹介を聞いている人の立場に立ってみて、どんな話に興味を持ってもらえるのか考えてから話すようにしてみてください。
話す時間は、1分以内に
次に大切なのは、話す時間です。長くてもせいぜい1分ほどにまとめたほうが無難でしょう。
例えば、ある人が転勤してきたとします。転勤してきた人は、そこにいる人にとってなじみがない方なので、多少長くしゃべってもいいでしょう。それでも1分も話すと長いと感じるはず。
以前にも書きましたが、スピーチは長いと思われたら、どんなに内容が良くても、印象が良くなくなります。もう少し聞きたかったと思われるくらいでちょうどです。受け入れる側は人数によりますが、さらに短めの自己紹介が求められるでしょう。
自己紹介の目的は、話しかけてもらうきっかけを与える
では、1分以内で何を話すべきか。ポイントは「全てを語ろうとしない」ことです。名前などの基本情報以外でも、生育地、学歴、趣味など言おうと思えば、いくらでも言えます。でも少し考えてほしいのです。「それは今言う必要があることなのか?」と。
私は、自己紹介の目的は、自分の様々な情報を、細かく相手に覚えてもらうことではない、と思っています。新しく出会う人に、このあと「話しかけてもらうきっかけを与える」こと。これさえできれば十分だと考えています。
例えば、「趣味は食べ歩きです」だけよりも「仕事ももちろんですが、職場近くのランチ情報をまず教えてください(受け入れる側なら「ランチ情報なら私に聞いてください」)。」の方が、ずっと話しかけやすいですよね。
自己紹介の場は、表面上は笑顔で取り繕っても、お互いのことを距離を置いて観察するようなムードになってしまいがちです。そんな空気を壊すきっかけを作るようにするのです。
出会ってからお互いを理解し合うには、ある程度の時間が必要です。細かい情報は、今後いくらでも話す機会はあるでしょう。だからこそ、ファーストコンタクトである自己紹介では、自分に関する話しかけやすい情報を会話のエサとしてまき、フレンドリーさを出すことで十分だと割り切るのです。
これを機に、自分の会話のエサは何か、ちょっと考えてみませんか?
この記事は、2019年1月から12月まで週刊東洋経済に連載したコラム「必ず伝わる最強の話術」に 加筆修正を加えたものです。
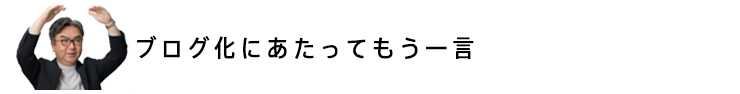
 松本和也(まつもと・かずや) / 音声表現コンサルタント・ナレーター・司会・ファシリテーター。1967年兵庫県神戸市生まれ。私立灘高校、京都大学経済学部を卒業後、1991年NHKにアナウンサーとして入局。奈良・福井の各放送局を経て、1999年から2012年まで東京アナウンス室勤務。2016年6月退職。7月から「株式会社マツモトメソッド」代表取締役。アナウンサー時代の主な担当番組は、「英語でしゃべらナイト」司会(2001~2007)、「NHK紅白歌合戦」総合司会(2007、2008)、「NHKのど自慢」司会(2010~2011)、「ダーウィンが来た!生きもの新伝説」「NHKスペシャル(多数)」「大河ドラマ『北条時宗』・木曜時代劇『陽炎の辻1/2/3』」等のナレーター、「シドニーパラリンピック開閉会式」実況に加え、報道番組のキャスターなどアナウンサーとしてあらゆるジャンルの仕事を経験した。株式会社 青二プロダクション所属
松本和也(まつもと・かずや) / 音声表現コンサルタント・ナレーター・司会・ファシリテーター。1967年兵庫県神戸市生まれ。私立灘高校、京都大学経済学部を卒業後、1991年NHKにアナウンサーとして入局。奈良・福井の各放送局を経て、1999年から2012年まで東京アナウンス室勤務。2016年6月退職。7月から「株式会社マツモトメソッド」代表取締役。アナウンサー時代の主な担当番組は、「英語でしゃべらナイト」司会(2001~2007)、「NHK紅白歌合戦」総合司会(2007、2008)、「NHKのど自慢」司会(2010~2011)、「ダーウィンが来た!生きもの新伝説」「NHKスペシャル(多数)」「大河ドラマ『北条時宗』・木曜時代劇『陽炎の辻1/2/3』」等のナレーター、「シドニーパラリンピック開閉会式」実況に加え、報道番組のキャスターなどアナウンサーとしてあらゆるジャンルの仕事を経験した。株式会社 青二プロダクション所属